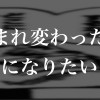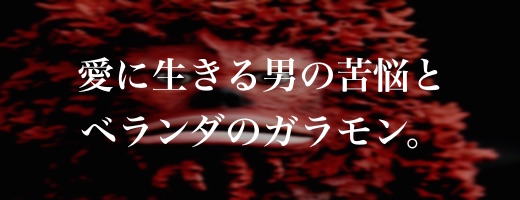
僕は愛に生きる男だ。
愛に生きるとは、許して生きるということである。
許さなければ、戦ったところで勝ち目のない人生を生きているのだ。
許すべき案件は多岐に渡る。
彼女様の暴力に始まり、僕が乗り込む直前に電車のドアを閉めたJR東西線の車掌や、気分よく歩いている時に足の小指をぶつけた事務所のホワイトボードの角など、数え上げると枚挙に暇がない。
そしてそのどれもが、訴訟を起こしても敗色濃厚である。
ホワイトボードに至っては、法的に訴訟を起こす機会すら与えられない始末だ。
先日コンビニで昼食の麻婆豆腐丼を買った際に、レジの店員が箸を付けてくれていなかった。
僕がそのことに気付いたのは、レンジでグツグツに温めた麻婆豆腐丼を公園で開けた、その時であった。
人は、そこにあって当たり前と信じていたものが無いとなると、実に大きな衝撃を受けるものだ。
落とし穴にハマる人は皆、自分が落ちていくことではなく、床がなかったことに驚くのである。
ボコボコと沸騰する麻婆豆腐丼を膝の上に乗せ、アチチなどと言いながら僕は、それはそれは筆舌に尽くしがたい虚無感を味わっていた。
この時点で、僕には選択肢が2つあった。
①さっき麻婆豆腐丼を買ったコンビニまで戻り、箸をもらう。
②事務所まで戻り、自分の箸を使う、である。
①は早々に却下した。
コンビニの店員が僕を見て、「こいつは素手で麻婆豆腐丼を食べそうだ」と判断した可能性があるからだ。
今からさっきの店に戻って箸の不在を言及した時に、「箸使うんですか!」などという顔をされた挙句中途半端に冷めた麻婆豆腐丼を食べるのは、いくらなんでも心に染み過ぎる。
場合によっては、「僕はあなたが箸を使わない人だと信じていたのに!」と一方的に理解し難い主張を投げつけられる可能性もゼロではない。
そんな新人類と出会う元気は、丼の蓋を開けてから箸の不在を知った僕には、残されていない。
となると、僕の選択肢は自ずと②の一択となる。
せっかくグツグツに温まっている麻婆豆腐丼がまさしく口惜しいが、事務所にも電子レンジがあるから、温め直しは可能である。
僕は腹の中に渦巻くコンビニ店員への怒りを感じつつ、麻婆豆腐丼をビニール袋に戻して歩き出した。
少し歩いたところで、突然物陰から自転車にまたがったおばちゃんが現れた。
ポケモンで戦闘が始まる時は、きっとこんな感じなのだろうなと思わせてくれる程度には、あまりにも突然の出来事であった。
信じられないかもしれないが、大阪のおばちゃんは、自分の自転車の前には絶対に誰も現れないと信じている節がある。
僕の彼女様も自転車に乗ると人格が豹変するから(悪鬼から羅刹になるのだ)、これは土着的な宗教に近いのかもしれない。
とにかく、そんなおばちゃんが飛び出してきたものだから、僕としてはたまったものではない。
おばちゃんの自転車はけたたましいブレーキ音を立てて止まり(手元がカバーで隠れていたから、実際にブレーキを握っていたかどうかは定かではない。もしかしたら、おばちゃんの叫び声だったかもしれない。)、僕を数十センチ吹っ飛ばした。
当然、一蓮托生の関係であったビニール袋も、数十センチ吹っ飛んだ。
「あーびっくりした」
おばちゃんの感想が素直すぎてびっくりした。
自転車に乗っていた自分が歩行者の脇腹に突撃したのだから、普通は謝るのが先ではないか。
僕は体を起こし、毅然とした態度でこう言った。
「すいませんでした。」
愛深く陳謝の姿勢を見せる僕に、おばちゃんはようやく「大丈夫か」と気遣いの言葉をかけた。
僕の体は大丈夫だ。
しかし麻婆豆腐丼が入ったビニール袋は少し離れたところに転がっていて、うっすらと見えるビニールの中の器は、先ほどまで僕の膝の上に居た彼とは明らかに違う角度で、大阪の大地にその身を預けていた。
「大丈夫です」
それ以外にどう答えろというのか。
これからこのおばちゃんが僕の事務所に来て麻婆豆腐丼を作ってくれるとでもいうのか。
そんなものばかり食べてちゃダメと、キンピラごぼうを大量に作ってストックされるのが落ちである。
走り去るおばちゃんのたくましい背中を視界の隅に捉えつつビニール袋を持ち上げる。
紅い。
明らかにビニール袋の内側が紅い。
なにやら豆板醤的に紅い。
きっと表面のラー油が少し溢れただけさと指で触れてみると、そこには明らかに半固体的な質量が感じて取れたのだった。
春の日は柔らかいが、街吹く風にはまだ冬の名残がしがみついている。
それは僕の手元の不本意の塊からも刻一刻と温もりを奪い、どこか遠い空の向こうに連れ去ってしまっていた。
僕の麻婆豆腐丼(元)の抱いていた熱量が、どこかの美女が干している下着の間を通り抜けることを心から祈っていると、近所の家のベランダに、ガラモンのようなおばちゃんが現れて布団をバンバンと叩き始めた。
愛の男はきっとその時、泣いていたのだと思う。