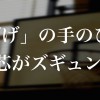シロが逝ったというメールが、今朝叔母から届いた。
昨年の冬ごろに上げていたブログに頻繁に登場していた、あのパンク顔の猫である。

シロは齢20歳を超える化け猫である。で、あった。
体が白いからという実に深遠なる理由でシロな名付けられたこの猫は、僕が小学生の頃から母の実家(僕の実家から徒歩20分)の作業場で、いつも何かの物陰からこちらを見ていたものだった。
シロが僕の近くに来てくれるようになったのは、ここ何年かのことだ。
特に僕が関東から引き上げてきてプー太郎をしていた1年間は、ほぼ毎日僕がシロのところに出向き、ご飯を上げてブラシを入れて、ひとしきりイチャイチャしながら仕事をするというスタイルが確立していた。
僕が大阪に事務所を構えてからは、僕の後を追ってプー太郎になったブラザーちゅわさんや、不可解なことに今だプー太郎を経験していないブラザーぷうちゃんが面倒を見ていたそうだ。
何より、誰も居ない時に仕事と家事の合間で世話に走っていた、母の尽力は大変なものだったろう。
今じんわりと、さみしい。
石垣島に引っ越す前に大阪で会ったブラザーちゅわさんが、「もう長くないと思う」と言っていた、まさにその通りになった。
もう本を読みながら、20分で辿り付ける距離を30分かけてゆっくりと歩いていって、あの開けにくい鍵を開けてコンクリイトの土間をどれだけ歩き回っても、シロは居ない。
夏の暑い日に道路の真ん中で寝ているシロをどかして車を走らせる手間もなければ、冬の寒い日にホットカーペットやカイロをかき集めて段ボールベッドに詰め込む苦労もない。
冷蔵庫の中の小魚とカツオ節を缶詰と混ぜて「ゴージャス飯だシロちゃん!」と一人で盛り上がることもない。
ああそうか。
シロは死んだのか。
シロ、お前死んだんか。
人や動物の死と出会うと、いつも思う。
僕らは自分が思っている以上に、相手のことを想っているのだ。
よく「ポッカリと穴が開いたような」という表現をするが、ポッカリとした穴が開くほどに、相手のことを想っていたのだ。
若くして親の介護をしている人も居れば、老老介護という現代社会の問題と戦っている人もいる。
突然大切な人を失うこともあれば、ゆったりとした時の中で順風の最後を遂げる人もいる。
いずれにしても、僕たちは本当に、人を想っている。
家族同然になった動物達のことも、想っているのだ。
そうして僕らの側から空に還ってゆく彼らは、最後に残った僕たちにあるものをくれる。
それは彼らと共に居たという「経験」と、それを活かすための「時間」である。
目の前に居るその人は、いずれ死ぬ。
君の前から消えて居なくなる。
声も匂いも笑い声も泣き声も、今この瞬間にしか触れられない。
そして自分自身もまた、そうだ。
死は日常である。
そして死を思うからこそ、僕たちには理解できることがある。
死神というと禍々しい印象だけれど、死というのは僕たちの心に大きな思いやりと力を与えてくれる、天使なのだと思う。
シロを連れて行ってくれた天使は、僕ら家族にもきっと、羽を落としてくれているのだ。
しっかりと拾い上げて、ついでにシロの毛も拾い上げて、ちゃんとポケットに入れておかなければ。
ああ、もう、言葉がない。
もっとずっとお前のことを書いていたいのに。
シロ、シロ。
さようなら、シロちゃん。
僕らの付き合いは短かったけど、楽しかったよな。
また会おうな。
愛してるよ。